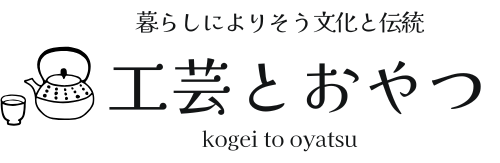播州織は兵庫県多可町や西脇市を中心に生産されている伝統的な織物。
江戸時代、日本各地で数多くの織物が発展しましたが、この伝統的な播州織もそのひとつです。
名前は聞いたことがあったけれど、播州織の商品をじっくりと見てみたのは、恥ずかしながら2024年のこと。
「ことりっぷ旅するマルシェ2024」というイベントでした。
持ってないみたいに軽いのに包み込まれているようなあたたかさがあって、とても感動したことをよく覚えています。
先染めの糸で織りなす
播州織の特徴は、糸を先に染めてから織り上げる「先染め」であること。
私が見せていただいた商品は、シャツやワンピース、ショールやバッグなど、比較的薄手のものでした。
実際に購入したtamaki niimeのショールは、伝統的な播州織をベースとしてつくられたもの。
個性的でありながらナチュラルな風合いの生地は、ていねいに染められた糸によって生みだされたのだなぁ、と実感しました。
播州織の歴史を調べてみると、そのはじまりは、江戸時代の中期なのだそうです。
西脇市のホームページには「「播州織」は江戸時代中期(11代将軍徳川家斉の治世)の寛政4(1792)年に比延庄村の宮大工飛田安兵衛(ひだやすべえ)が京都西陣から織物の技術を持ち帰ったのが起源と伝えられています。」1とありました。
西陣織がルーツなんですね。
播磨国(現在の兵庫県南西部)は温暖な気候で、江戸時代中期から綿花栽培が行われていました。また、加古川、杉原川などの河川が集まり、染め物に必要な水資源も豊富にありました。そこに織物の製造技術を得た飛田安兵衛によって織機がつくられ、播州織が発展したとされています。
明治後期になると、織機は機械化された「力織機」が広く普及するようになりました。
生産力が高まったことで工場での大量生産が可能に。
そして播州織は、昭和の時代に黄金時代を迎えることとなりました。
しかし、播州織の現状は、多くの伝統工芸品と同じく減少傾向にあります。
それでも、伝統的な織物に新たな息吹を吹き込み、現代にマッチしたすてきな商品も生みだされています。
わたしがイベントで出会えたアイテムも、そのうちのひとつ。
これからも播州織に注目していきたいと思います!
播州織のこれから
地域ブランドとして認定されている播州織は、SDGsへの取り組みも積極的です。
公益財団法人 北播磨地場産業開発機構のホームページによると、繊維廃棄物の再資源化への取り組みや、余った糸を再利用できるシステム「アレンジワインダー」についてなどが紹介されていました。
アレンジワインダーは「第1回ものづくり日本大賞」において、最優秀の内閣総理大臣賞を受賞されたのだそう。
織物の仕組みは、織機にまっすぐぴんと並ぶように張られた経糸(たていと)の間を、緯糸(よこいと)で交差するように織っていく、というものです。まさに、縦の糸と横の糸で織り込んでいくのですね。
織機で製造する場合、まず織機に経糸を準備します。経糸を並べる本数や長さは布の幅や長さに直接影響しますので、慎重に行わなければなりません。手間と時間のかかる作業ですが、経糸を変えたい場合は、当然、この工程をはじめからやり直す必要があります。
では、アレンジワインダーは、生産工程にどう影響するのか。
異なる糸をつなぎあわせ、1本の糸として巻き上げられるアレンジワインダーの登場は、経糸を付け替えるという生産コストを抑え、デザイン性も広がると期待されているのだそうです。
生産性を高めながら、デザインの幅も広げていく。
アレンジワイルダーをはじめとする、残った糸に新たな命を吹き込むというシステムは、これからも播州織を支える大きな柱となっていくのではないでしょうか。
【参考ページ】
・播州織工業協同組合
・兵庫県西脇市|地場産業「播州織」
・公益財団法人 北播磨地場産業開発機構